メンバーたちの「想い」と「挑戦」をお届けするMembers File。
今回は、開発グループのメンバーにインタビューを行い、日々の業務を通じて成長できていること、そしてその成長支援の取り組みについて聞きました。
Interview Profile
株式会社ストアフロント
サービスデベロップメント部
開発グループ
▶グループ統括(シニアエンジニア) T.N 2019年1月入社
▶サブスクサービス開発担当(サブリーダー)K.S 2022年11月入社
▶toC向けサービス開発担当 M.K 2025年2月入社
▶店舗運営者向けサービス開発担当 J.K 2025年1月入社
▶デザイナー A.T 2023年11月入社
Q:開発を担当しているサービスと、メンバー構成について教えてください

エンジニアは私を含めて計4名です。
toC向けのデジタルサービス『ダレカナブロック』と『ポケットバックアップ』の開発メンバーが1名、店舗運営者向けのサービス『モバイルウインドウ』の開発メンバーが1名、サブスクサービス『SubscLamp』の開発メンバーが1名です。
そして、各サービスのデザインを担当するデザイナーが1名います。
私たちは少数精鋭のグループなので、各プロダクトともに優先順位をつけて開発に取り組んでいます。
優先順位をつける際、まず重要なのは「会社の売上へのインパクト」という視点です。これが大きな優先順位を決める軸になります。また、「サービスを24時間365日運営する上での安定性」も非常に重要です。サービスが安定して稼働し続けることが前提となるため、安定性に支障をきたす可能性があれば、緊急度が高いと見なし優先順位を上げて取り組みます。
Q:各サービスで取り組んでいる具体的な開発について教えてください
toC向けサービス『ダレカナブロック』『ポケットバックアップ』

toC向けサービスでは、主に2つの開発に取り組んでいます。
1つ目は、機能改善に関する開発です。例えば、サービスを解約したユーザーからアンケートを取得し、データをもとに現在のニーズを把握する仕組みを作る開発があります。これは、直接サービスの利便性が向上する開発ではありませんが、ニーズを把握することで、サービスをよりよくすることに繋がります。さらには、将来のサービス改善や新しいプロダクト開発に役立つ材料にもなる重要な開発です。
2つ目は、サービスの健全な運営を維持するための開発です。データベースの定期的なアップデート後、サービスが正常に動作するかを確認し、セキュリティ面を強化しています。これにより、個人情報流出のリスクを防ぐことに繋がるなど、企業の信頼を守ることができます。
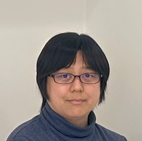
現在優先度高く取り組んでいることは、運用保守業務です。具体的には、サービスが安全に運用できるよう、データベースのバージョンアップを行っています。古いバージョンのままだとセキュリティが脆弱になってしまうため、サービス品質を維持・向上させるためには欠かせない業務です。
入社してまだ2ヶ月弱のため、具体的な業務に入る前には、サービスを理解することに努めました。サイトとアプリを実際に操作し、一通りの動作を把握した上で、ソースコードを見ながら動きを理解していきました。分からない点があれば、メンバーに確認をしながら進めています。
店舗運営者向けサービス『モバイルウインドウ』

『モバイルウインドウ』については、サービス品質向上を目指し内製化を進めています。これによりシステムの安定性を向上させ、より信頼性の高いサービスを提供できるよう取り組んでいます。

1月にストアフロントにジョインし、今後『モバイルウインドウ』の開発業務全般を担当できるよう、まずは仕様を学ぶことから取り組んでいます。システム規模が大きいため、現在もキャッチアップは続いています。
入社後最初の1ヶ月は、既存の仕様書をもとにシステムに触れながら理解を深めていきました。その後、2カ月目からは『モバイルウインドウ』を使用する店舗運営者の視点に立ち、業務の流れを把握し、システムが設計通りに動作するかを確認するシナリオテストを行っているところです。
サブスクサービスを作成できる『SubscLamp』

『SubscLamp』では、クレジットカード決済時の本人確認を行う「3Dセキュア」の導入開発を進めています。
4月から法律で導入が義務化されているため、この対応を行わないと、サービスへの支払いができなくなります。そのため、収益に直結する重要な開発として最優先で取り組んでいるところです。
Q:メンバー同士のコミュニケーションはどのように行っていますか?

今までは、コミュニケーション頻度は多くありませんでした。プロダクト毎に使う技術が異なり、個人で完結できてしまうためです。
ただ、グループ全体の開発力を底上げするためには、メンバー同士のナレッジ共有が重要だと感じ、プロダクト単位ではなくグループ全体で朝会・夕会を設け、1人1人の取り組みを共有する機会を増やしました。これにより、メンバー間のコミュニケーションが強化され、知識やノウハウの共有が進んでいます。
Q:朝礼・夕会がどんな取り組みなのか教えてください
進捗を共有し合い、全員で問題解決をしながら目標達成を目指す

朝会・夕会の目的は、目標を計画通りに達成するために、個々のスケジュール管理の精度を高め、問題を早期に発見し解決することです。
エンジニアは黙々と仕事を進めがちですが、その結果思考が停滞し効率が落ちることがあります。そこで、進捗や課題を共有する場として朝会・夕会を導入しました。各自の取り組み内容や抱えている課題、進捗状況を共有し合い、みんなで改善点を見つけて解決しています。
また、朝会と夕会では役割が異なり、朝会では「今日やること」を明確にし、夕会ではその「進捗」を確認します。
朝の段階で設定した計画が夕方にどうなっているのかを振り返ることで、計画の精度を高めることができます。もし計画の見積もりが甘く、予定通りに進まなかった場合は、その原因を振り返り、スケジュール感や工程の解像度が不足していたことを認識しながら、改善策を検討していきます。
Q:朝会・夕会の取り組みを通じて、どのような効果を感じていますか?
フィードバックから新たな視点や気づきを得ることで、スキルアップにもつながっています

開発スケジュールを、より解像度高く把握できるようになりました。1人で計画を立てるだけでなく、それをメンバーに共有することで、「具体的には?」と質問されることが増え、自分の理解不足に気づきやすくなります。
また、進め方についてフィードバックをもらえる点も大きなメリットです。具体的な実装内容を共有することで、新しい視点や意見を得られる点も、技術面での成長に繋がっていると感じます。
毎日振り返りをすることで早い段階で問題が見つかり、次の行動に活かせています

入社当初は、1日2回って本当に必要なの?と思いましたが、業務を計画的に進めるためには非常に有効だと感じています。
朝会では、その日行う業務を整理してアウトプットすることで、時間の割り振りやタスク管理が体系的にできるようになりました。夕会では、1日のタスクを振り返り、次に繋がる改善点を早い段階で見つけることができています。
業務理解を深めるとともに、自己管理能力も身に着いてきました
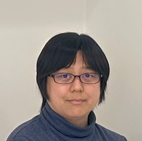
私は入社して間もないため、頻繁にコミュニケーションがとれる機会は業務理解を深める上でとても助かっています。
まだ先の作業を見通すことができていない部分があり、Nさんから都度指示をもらいながら進めています。翌日のタスクは設定できても、来週の計画はまだ不鮮明な部分があるんです。
その点、朝会や夕会で都度確認できるので、今後自分で計画を立てるための整理が進んでいると感じています。
メンバーからアドバイスを受けることで迷いが減り、着実に前に進めるようになりました
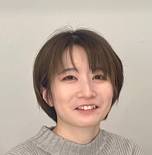
一番の効果は、タスクが整理され迷いが減ったことです。
朝会・夕会に参加するまでは、タスクが積み重なると優先順位がわからず困ることが多々ありました。今では朝会に向けてタスクを整理する習慣がつき、周囲からのアドバイスを受けることで、よりタスクが整理され迷うことが減りました。また、グループ全体に意見を共有するため、複数の視点から気づきを得られ、タスクの精度が向上していると実感しています。
夕会では、朝会での進捗を振り返り、計画通り進まなかった理由を考え、翌日の計画に活かすことで、着実に前進できています。
▼朝会・夕会の取り組み関するブログ記事もあわせてご覧ください
Q:ストアフロントの開発グループで、ご自身の成長を感じる点はどこですか?

技術面でも成長を感じていますが、それ以上に「目的や根拠を持ってサービスを作る」考え方が身についたことが一番の成長だと思っています。
最初の頃は、つい多くの機能を盛り込みたくなることがありましたが、どのような目的でそのサービスが使われるのかを考え、ディスカッションを重ねることで、本当に必要な機能を絞り込むことの重要性に気付きました。今では、まず目的を把握し、その目的に基づいて開発を進めることができるようになっています。

私の場合は、今行っている業務が今後どんなことに繋がるのかを見据えて動けるようになったことが、大きな変化だと思います。
担当している『モバイルウインドウ』の仕様理解とテストは、システムが大きいため簡単ではありません。最初は心が折れそうになることもありました。
ですが、今後、開発業務全般を主体的に担うための事前準備として必要不可欠であること。そして、今後会社にとっても重要な資産になると認識できたことで、考え方を変えて取り組めるようになりました。今では、大変さの中にもやりがいや楽しさを感じられるようになっています。
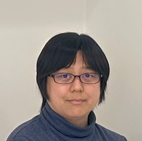
入社して1カ月半が経ち、日々のコミュニケーションを通じて、まずは自分で調べて考え、それを発信することが増えました。
まだ分からないことは多いですが、質問する際は事前に調べて自分なりの考えを伝えることを大切にしています。これにより学びが深まり、次に進む力がついてきました。自分で考える習慣が身についたことで、自然と解決策を見つけられるようになったとも感じています。
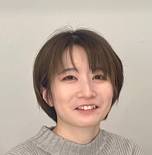
自発的なコミュニケーションのアプローチが増えたことが、最も大きな変化だと思います。
コミュニケーションが活発な組織風土の中で、積極的に周囲と関わるようになり、その結果スキル面での成長を実感しています。 周りのメンバーから積極的にインプットを受け取り、それを自分の知識として吸収するだけでなく、アウトプットする回数も増えました。
単に知識が増えただけでなく、その知識を実際の業務に活かす力が身についたと感じています。
Q:キャリア形成におけるメンバーへの支援体制について教えてください

月1回、各メンバーと1on1ミーティングを実施しています。
目的の1つ目は、「目線合わせ」です。会社として期待していることを共有し、キャリアに必要なステップを整理しています。例えば、次のステップとして専門職を目指していくのであれば、そのために必要な準備を話し合う場にしています。成長目標を日々の業務に組み込みながらサポートを行っている形です。
2つ目は、「目指す方向性の更新」です。技術面だけでなく、個人の目標や興味は日々変わるため、毎月の1on1でキャッチアップをしながら情報をアップデートしています。
現在の開発グループは、第二創業期のような状況です。ルールが整っていない点は、メンバー全員がそのルールを作り上げていけるチャンスとも言えます。自由な発想で新しいものを生み出しながら、1人1人がキャリアを描くことができる環境だと思っています。

私自身、ストアフロントで2年間働いてきて、エンジニアとしてのスキルアップは日々の業務を通じて叶っています。
毎月の1on1では、インフラ領域にも興味があることを伝えたことがきっかけで、今後その分野も任せていきたいと言ってもらえました。こうした機会を通じて、業務範囲が広がっているので、改めてチャレンジできる環境だと実感しています。
また、フレキシブルに動ける環境が整っているので、形式にとらわれず無駄なく効率的に進めることができています。この環境のおかげで、自分のレベルを早く上げられていると感じているので、誰でもエンジニアとして成長できる場だと思います。
Q:開発グループとして大切にしている姿勢や行動について教えてください

まずは、問題を自分事としてとらえ、自責の念を持つことです。
何か問題が起きた時、その原因をしっかり説明できるようにすることはとても大切です。あいまいな対応をすると、のちのちサービス利用者の不満や機能のバグに繋がる可能性があるからです。
問題が発生したときは、感情的にならず、どうすれば改善できるかを自分事として考え、行動することを大切にしてほしいと思っています。

自走力は必要だと思います。
Nさんが言っていたように、開発グループにはルールや決まりが少なく、その分自分で考えて行動する力が求められます。1人1人が自走力を持って仕事を進めることで、開発スピードも高まり、グループ全体の成長にも繋がります。こうした環境で成長したい方には、きっとやりがいを感じてもらえる組織だと思います。

技術面でいうと、新しい技術には興味を持ってほしいです。
技術は日々進化しているので、それに順応できることは良いエンジニアになるために必要です。ただ、古い技術にも良いものはたくさんあります。重要なのは、目的や状況に応じて最適な技術を選択できることです。新しい技術を学ぶことは重要ですが、現在使っている技術と比較して、どちらが適切かを判断できるスキルも大切にしてほしいと考えています。
Q:最後に、今後どんな組織を目指しているか教えてください
自由な発想を活かし、エンジニア主導でいいプロダクトを作れる組織に

ストアフロントの魅力は、「やりたいことができる環境」があることです。
決められたことをこなすだけでなく、まだ整っていない部分を整え、パイオニアとして新しい道を切り開いていける環境があります。そのためには、自分から率先して作り上げていく姿勢が大切です。私が決めたことを実行するのではなく、メンバー同士が対等な立場で意見を出し合い、共に進めていくような組織を作っていきたいと考えています。
型に縛られず、自由な発想で良いプロダクトをエンジニアが中心となって作り上げていく。そして、最終的には世の中の「ありがとう」に繋げていける集団を目指したいと思っています。

